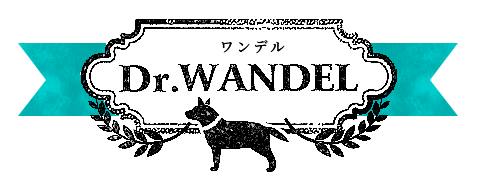【獣医師が監修!】
ワンちゃんのお口の臭いが気になる…
犬の口臭の原因と対処法とは?

飼い主さんがいつも愛犬と過ごしていて気になることの1つに、口臭があるのではないでしょうか。
愛情表現の一つとして顔を舐めようとしたとき、一緒にいると部屋の中でふわっと口臭が臭うときなど、飼い主さんが気になるタイミングは様々だと思います。
口腔内トラブルは直接命にかかわることは少ないため、ついケアや治療が後回しになることが多いですが、犬の歯周病や、口臭を放つ原因となる病気によって、ごはんが食べられなくなることもあります。最悪の場合は、下顎の骨折や全身状態の悪化などにも繋がり、寿命を削ってしまうこともあるのです。
歯周病やその他の病気のサインかもしれない犬の口臭について、そして不快な口臭を予防するケアについて、お話しさせていただきます。
この記事の監修

葛野莉奈 獣医師 /
かどのペットクリニック院長
麻布大学獣医学部獣医学科卒業。神奈川県内動物病院、会員制電話相談動物病院などの勤務を経て、横浜市内にかどのペットクリニックを開院。現在、かどのペットクリニック院長を務める。
ASCながたの皮膚科塾修了。
麻布大学獣医学部獣医学科卒業。神奈川県内動物病院、会員制電話相談動物病院などの勤務を経て、横浜市内にかどのペットクリニックを開院。現在、かどのペットクリニック院長を務める。
ASCながたの皮膚科塾修了。
皮膚科診療や子犬・子猫診療、産科診療を得意としておりますが、院内では一般的な一時診療として内科診療、歯科診療なども広く診させていただいております。 ワンちゃんと一緒に過ごす生活に後悔の無いよう、治療方針等ゆっくりお話をしながら、病気や治療について飼い主様にもしっかり理解していただけるよう心がけております。 この記事を読んで、少しでもワンちゃんの口腔トラブルや口腔ケアにご興味を持って頂き、歯周病の予防につなげて頂けたら光栄です。
口臭の原因・考えられる病気って?
犬の口臭は健康な状態でも全くの無臭ということはありません。人間と違って、犬には口臭がすぐに消せるような歯磨きペーストなどもありません。
飼い主さんが嫌に感じる口臭の原因として、口腔内の汚れが原因となった歯石や歯垢、それに集まる細菌の繁殖などが考えられます。
そして、犬の口腔内で悪臭が発生するほどの細菌の繁殖に至ってしまう原因には、汚れだけでなく、背景に病気が潜んでいる可能性があるのです。
犬の口臭の変化に気づけると病気のいち早い発見にもつながります。
ではその変化によって考えられる犬の口腔内の異常や病気とはどんなものなのでしょうか。
原因1:お口の中の環境の悪化

犬の口腔内で食べ物の残りかすなどが付着したままになることで、その周りに細菌が集まったり、歯石を形成したり、歯肉炎や歯周病を起こしたりします。
歯の汚れはプラークと呼ばれることがよく知られていますが、このプラークに含まれる細菌が歯肉や歯根近くの歯周で悪さをします。
犬の口臭はこの細菌が原因となるものが多いと言われており、特に歯と歯茎の間にある歯周ポケットの中でも空気に触れない部分に集まる嫌気性菌は、アンモニア臭に近い悪臭を放つとされています。
歯肉炎は進行することで歯周炎を起こし、犬の歯や顎の骨を溶かしてしまったり、副鼻腔と呼ばれる頭蓋骨の中で空洞になっている部分に膿が溜まってしまい、鼻汁として排出されたり、破裂して皮膚を突き破って排出されたりするケースもあります。
この場合に、犬の口腔内で繁殖した細菌やその炎症が全身にも影響を与え、心臓などの口腔から離れた器官でも害を及ぼすことがあります。
顎の骨を溶かしたり、全身の状態が悪くなったりする前に気付いて、麻酔下での歯石除去のケアや抗生剤の投与、そして場合によっては歯周炎の原因になってしまっている歯の抜歯などの処置を行うことで、進行してさらなる害を及ぼすことを止めることが出来ます。
日常的なケアでよりよい状態を保つことはもちろん大切ですが、早い時期に犬の口腔内の異変に気付くためには、普段から犬の口臭についても気をつけておくことが大切です。
少しでも歯周病が軽度な状態のときに気付いて処置を行った方が、犬の体への負担も少なくて済みます。
原因2:お口の中以外の問題

犬の口腔内環境の異常以外でも口臭に繋がることはあります。
例えば、腎疾患などで脱水が進んでいる場合、水分の不足に伴い、犬の口の中の水分も減って乾燥することで、口臭が増して感じることがあります。
下痢や嘔吐などで脱水が進んだせいで口臭を感じることもありますし、消化不良を起こし、消化器にガスがたまってげっぷやおならとして排出された際、未消化なもののにおいとしてげっぷをしたばかりの口臭をくさく感じる場合もあります。
この場合、口臭の原因となった疾患の対処をする必要があります。
例えば脱水が原因であれば、定期的に脱水の有無を検査した上で、点滴などで水分を補うことが挙げられます。
脱水の原因が下痢や嘔吐なのであれば、消化器症状を改善すべく治療をしなければなりません。腎疾患が原因であれば、腎疾患の治療を要します。このように、脱水となった原因に応じた治療が必要になるため、検査などで判明させる必要があるでしょう。
また、体質的に胃腸が弱く、ごはんが合わずに常に消化不良を起こしている場合、その子の消化機能に適したごはんを選ぶ必要があります。
人でも胃腸の強い人、弱い人がいるのと同様、犬も消化機能の害が出にくい個体もいれば、少しの変化などでも不調として現れる個体、消化吸収しやすいごはんでないと便の状態がよくない個体と様々で個体差があります。
常にお腹がぐるぐると鳴る音がしている、げっぷが多い、悪臭を感じる、軟便であることが多いなどの場合は胃腸が弱い個体である可能性が高いため、かかりつけの先生に相談してみることがおすすめです。
このように口臭の原因がお口の中以外の問題にある場合、犬の口腔ケアは口臭対策に直結しませんが、口腔内の環境も悪いと、原因が重なって口臭がさらに臭くなることもあります。
愛犬の健康のためにももちろんですが、一緒に過ごす上で、飼い主さんが不快に思うことのないよう、口腔内のケアをして衛生的にしておく必要があるでしょう。
原因3:食べ物

犬の口臭に影響するものの一つとして、食べ物にも注目する必要があります。
原因1で口腔内環境の悪化の際に、食べ物の残りかすなどの付着が原因となる可能性をお話しさせて頂きました。
軟らかいごはん、いわゆるウェットフードは犬の口の中にとどまりやすく、歯の隙間などに入り込み、口腔内環境を悪化させやすいということはご存じの方が多いと思います。
犬はもともと肉食で、切り裂いて細かくすることを目的とした歯のため、人間のようにすりつぶすことが目的の歯の構造と少し異なります。
そのため、軟らかいごはんや食べかすなどは口腔内に残ってしまいがちです。
ドライフードであれば問題無いと思われがちですが、食べ物である以上、食べかすが残ってしまいますので、日常的なケアは必要といえるでしょう。
そして、犬の口臭に繋がる原因でもうひとつ、忘れてはならないのが食糞です。
便はもちろん食べ物ではありませんが、食糞をする習慣がある犬は、日常的に糞を口にしているため、口腔内から糞のニオイが口臭として臭うことがあります。
糞が軟らかく、歯周ポケットなどに残り続けてしまう場合、食べかすと同様で細菌の繁殖の原因にもなり、歯周病に繋がることが多いのです。
衛生的にするために、日常的なケアをすると同時に、ニオイを除去するために、口腔内のニオイを軽減できるようなよい匂いのガムなどを与えるのもよいかもしれません。
また、食糞自体を防いであげるために、しつけの一環として、食糞をしたら注意をすること、空腹から食糞を行っているのであれば食事量を見直してあげること、ごはんが合っていないせいで食糞をしているのであれば食事内容を見直してあげることなども同時に行う必要があるでしょう。
どんなケアや対策をすればいいの?
犬の歯周病の予防のためにも口腔内の衛生状態をよい状態で保つためにもケアや対策などは大切ということをお話しさせて頂きました。
では、どんなケアや対策をすればよいのでしょうか?
ケアや対策がわかっても、犬の性格によってはさせてくれない子や、飼い主さんのライフスタイルによってはそれが難しいという場合もあるかもしれません。
その場合、犬の歯周病は避けて通れないものになってしまうのかというと、そんなことはありません。
ケアや対策は様々です。
お家の子に合った方法を選ぶこと、そしてまだまだお家に迎えたばかりの飼い主さんは、これからケアをしやすくするために、犬との生活や関係を見直して、長い犬との生活の中で少しでもケアが出来る期間を作れるよう、準備をしていきましょう。口内ケアができていれば、歯周病になってしまい、犬の健康や寿命を脅かすことになってしまったという最悪の事態を防げるでしょう。
ではどんなことに気をつけていけばいいのか、お話しさせて頂きます。
まずは食べ物の確認を

犬の口臭に繋がる原因となる食べ物を見直してみましょう。
先ほどお話させていただいた通り、軟らかいごはんはドライフードと比較して、犬の歯の構造状、口内に残ってしまい歯周病の原因となりやすいです。
若い子でどんなごはんでも食べてくれる場合、ドライフードを出来るだけチョイスすることで、歯の間に食べかすやごはんが入ってしまうことを予防できます。
ただし、ドライフードにしてもかみ合わせや歯並びなどの兼ね合いで、それでもごはんや食べかすが残りやすい犬もいますので、食後などに飼い主さんがしっかりチェック出来るとよいでしょう。
どうしても高齢で消化機能に問題があり軟らかいごはんしか食べられない子もいると思いますが、その場合は、よりしっかり口腔内のケアを重点的に行うようにしましょう。
また、食べ物の与え方も注意が必要です。
飼い主さんの使った食器を一緒に使ったり、分け与える際に飼い主さんの口でかじったものを与えたりはしていませんか?
人間の口腔内に存在する細菌と犬の口腔内に存在する細菌は異なるため、食器や口移しなどを通じて人間の口腔内の細菌が犬の口腔内に入ると、増殖して口腔内環境が悪化し、歯石や歯周病の原因になることがあります。
もちろんその場合、口臭も伴うケースが多いので注意が必要です。
基本的に飼い主さんが口にするものと犬が口にするものは別のものを用意するようにしましょう。
簡単なデンタルケアから始めよう!

口臭だけではなく、歯周病を予防するために、犬の口腔内のケアとして、歯ブラシでしっかりと歯磨きをすることは良いことです。
しかし、いきなり犬の口の中に歯ブラシを入れて磨くことは、犬も抵抗してしまい難しいでしょう。
ではどうしたらよいのでしょうか。
まず、若齢の犬であれば、しつけもかねて、まずは口周りを触らせてくれるよう、少しずつ慣らしていきましょう。
徐々に慣れてきたら、指サック型のケア用品で口の中に手を入れる、そして奥の方まで触れるようになることを目標とし、そして口の中に歯ブラシを入れることが出来るように練習するとよいと思います。
最終的に、奥歯まで歯ブラシで磨けるようになれたら理想的です。
もう成犬で、どうしても口周りを触らせてくれない場合は、歯ブラシ以外でも口腔内のケアをして歯周病を予防できる犬用のアイテムがたくさんありますので、歯ブラシに代わるものを探してみましょう。
例えば、噛むことで歯垢がとれる歯磨きガムや、加齢などによる唾液量の減少によって口腔内環境が悪化してしまうケースに有効な口腔内の衛生状態を良好に保つ液体状のアイテムもあります。
歯磨きケアのような役割のアイテムが難しければ、口腔内の状態を整えるようなサプリメントもあります。
犬の性格や、ライフスタイルに合ったケアの方法を選んでみてください。
歯ブラシでのケアが難しい場合はかかりつけの獣医師の先生に相談してみることをおすすめします。
飼い主さんがご自身で探す場合に気をつけたいのが、歯ブラシ代わりにおもちゃや硬いものを与える場合です。
硬すぎるものであると、犬の歯が摩耗や欠損してしまい、口腔内環境が悪化してしまうケースがあります。
また、噛むおもちゃなども壊して誤飲してしまうこともあるため、歯磨きの用途以外のものを選んで与える場合には、使い方に注意が必要です。
ブラッシングでさらにケアを

無理なく出来る口腔内ケアのアイテムが見つかっても、徐々に歯ブラシも慣らしてブラッシングでのケアもできるようになりましょう。
ブラッシングが、なぜ歯周病予防に効果的と言われているのでしょうか。
それは食べかすを掻き出す目的だけではありません。
歯石の付着や、歯周病が少しずつ進行していくと、歯肉と歯の間に歯周ポケットと呼ばれる溝が生じ、少しずつその溝が深くなっていきます。
歯周ポケットが深くなりさらに食べかすがたまるようになると、食べかすが蓋になり、溝の一番深いところに嫌気性菌と呼ばれる菌が増殖しやすい環境ができてしまうのです。
この嫌気性菌は口腔内の悪玉菌とも呼ばれ、アンモニアのような口臭の原因になり、歯周病の原因とも言われています。
この嫌気性菌が増殖しないよう、日常的に食べかすをしっかり掻き出すと同時に、細菌も一緒に掻き出してあげる必要があります。
この悪玉菌を増殖しないようにするには、物理的に歯周ポケット周辺をいつでも衛生的にしておく必要があります。
歯周ポケット周辺を掻き出しやすいよう、犬用でも歯ブラシが部分的に長く柔らかい毛が埋め込まれていることで、歯肉を傷つけないようにしながらケアが出来るようなアイテムも存在します。
歯周ポケットの深さや歯肉の出血のしやすさなども、歯周病の進行具合や、口腔内の状態によって個体差があります。
その子に合った歯ブラシを選ぶと、犬も歯ブラシに対して嫌な思いをすることなくケアが出来るでしょう。
中々口臭が無くならない…動物病院に連れてった方がいいの?

いろいろなケアを試してみても口臭がなくならない場合、もしかしたら歯周病以外の病気も含め、口臭の原因が目に見えない部分に存在している場合や、歯根の奥まで歯周病が進行している場合など、何か他に原因があるのかもしれません。
ケアをしても、歯石が残っていると悪臭の原因にもなり、しっかりと付着してしまった歯石は麻酔下での歯石除去が必要となる可能性が高いです。
また、歯周病が進行してしまっている場合、抜歯や抗生剤の投与などをしないと口臭が除去されない場合があります。
口臭がずっと残る場合は、全身状態を含め、動物病院を受診することをおすすめいたします。
臼歯と呼ばれる口の奥の方は、飼い主さんだと嫌がってよく見せてくれないこともありますし、顎の小さい犬などでは口の中自体なかなかゆっくりみることが難しいこともあります。
口臭があると言うことは何らかの身体の異常のサインであるケースが多いため、見過ごすと全身状態を悪化させてしまうことや、最悪の場合、死に至らせてしまうことがあるので、速やかに受診して頂くことをお勧めします。
まとめ
最悪の場合死に至る可能性もある歯周病や、疾患など、犬の体のSOSサインであることの多い口臭と、口臭の予防方法についてお話しさせて頂きました。
口腔内の異常はすぐに命にかかわりにくいため、後回しにしがちですが、犬が健康に長生きするために口腔内の衛生状態を良好に保つことはとても大切です。
まだきれいだから良いというのではなく、良い状態を保てるように愛犬に適したケア方法を見つけ、最終的にはブラッシングでのケアが行えるよう、飼い主さんも頑張りましょう。
そして、犬の口臭で飼い主さんも悩まされることなく、日々一緒に楽しく過ごせたら良いですね。
参考文献:犬の治療ガイド2020 私はこうしている(EDUWARD Press)
犬と猫の治療ガイド 2015 私はこうしている(interzoo)